美しさは信頼から生まれる?

こちらはコロナ禍前に訪れたロシア・サンクトペテルブルクの駅。特に日本のような親切なアナウンスは無く、電車の扉も無言で突然閉まるので、少しでもタイミングを間違えたら挟まれてしまう!と異様な緊張感で乗っていました。
皆さんは今年、長いお休みを取られましたか?
私は例年、夏の終りから秋ごろに遠出の旅行を計画することが多かったのですが、今年は我が家の愛犬がまだ1歳ということもあり、近場での社会化トレーニングを優先することにしました。
そのせいか、最近は過去に訪れた国での記憶をぼんやり思い返すことが増えています。思い出すのはもちろん、訪れた場所そのものもありますが、意外と強く記憶に残っているのは、そのときの自分の精神状態です。
特に海外の街を歩いていると、なんとも言えない不思議な感覚に包まれることがあります。それは、少し緊張しているのに、同時に心が解き放たれているような、ちょっと矛盾した感覚です。
その緊張の多くは、「スリに遭わないように」とか「道を間違えないように」といった、不慣れな環境への警戒心から来るもの。でも同時に、日常ではなかなか味わえない心の軽やかさもある。旅行という非日常に身を置けば、誰しも心が解放されるのは当たり前だと思いますが、私が感じたのは単なる休暇の開放感とは少し違う、心の底で縛りがほどけたような軽やかさでした。
そして、この心の軽さが印象深かったのは、観光地よりもむしろ駅や公園といった、その街の日常が垣間見える公共空間にいる時だったなと、ふと気づいたのです。
では、その「縛りがほどけたような軽さ」は、一体どこから来ていたのでしょうか。
私がこれまで訪れた国々の公共空間には、ある共通した雰囲気がありました。例えば駅では、けたたましいBGMもなく、アナウンスも最小限。遠くから電車の走行音が近づいてくるのを耳にしながら、人々はごく自然に電車を待ちます。また、注意書きや細かな案内の貼り紙は最小限で、空間そのものがすっきりと感じられます。
この感覚に触れた後で日本の日常に戻ってくると、「足元にご注意ください」「手すりにおつかまりください」「駆け込み乗車はおやめください」「忘れ物のないようご注意ください」といった絶え間ないアナウンスや、無数の注意喚起や案内の張り紙が目に付きます。それは紛れもなく日本の丁寧さの表れなのだと思うと同時に、自分で判断し行動する余地を、少しずつ奪われているような息苦しさを感じてしまうのです。
海外の環境は、日本に比べると不親切に映ることもあります。けれど、それは「いちいち言わなくても、あなたならわかるでしょ」という適度な放任に近く、むしろその感覚こそが私の心を軽くしてくれていたのだと思います。
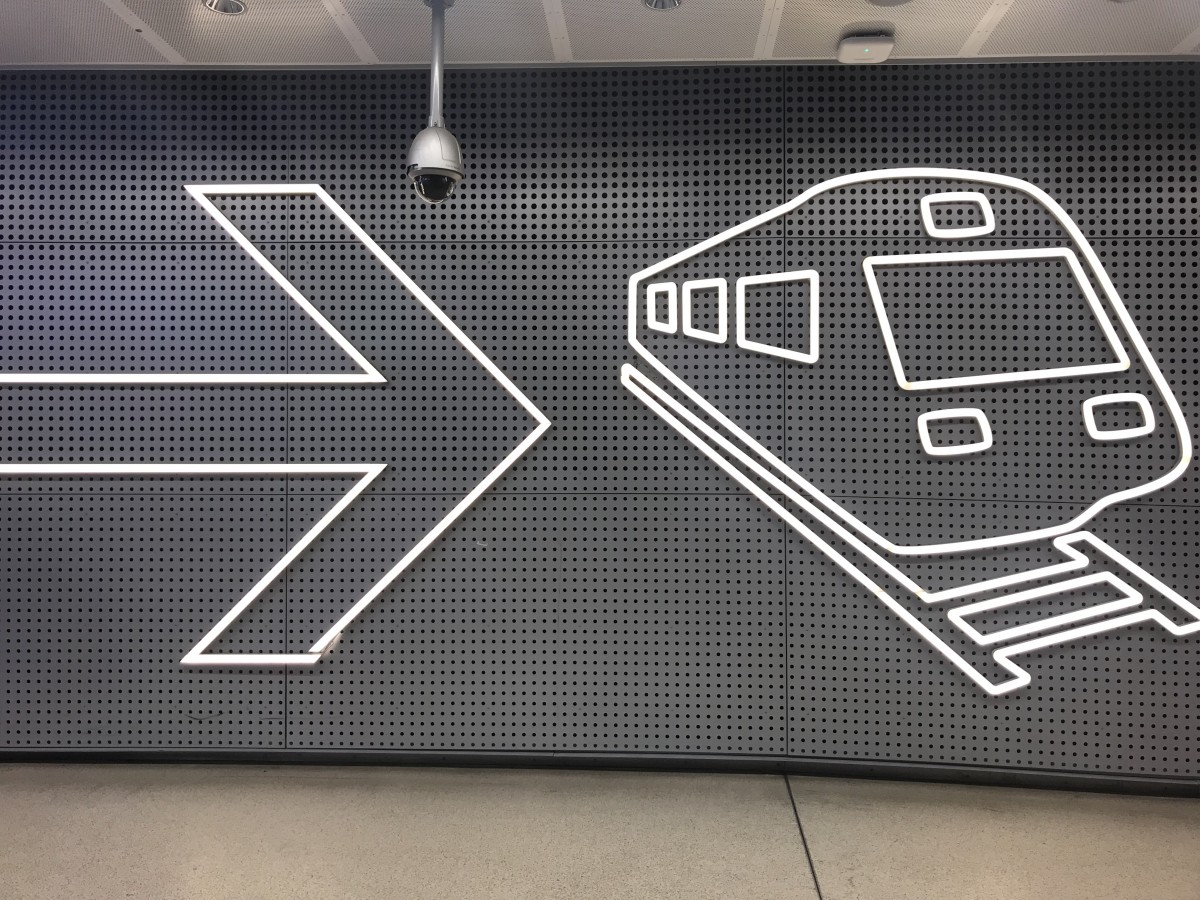
何度見ても惚れ惚れする、フィンランドの公共空間の表記。矢印の方向に行けば駅に行けるということがシンプルな絵で一目瞭然。余計な物が削ぎ落とされた案内板だと感じました。
日本人は他人を信頼するのが苦手?
では、なぜ日本の街は、注意喚起の看板やアナウンスで溢れているのでしょうか。このテーマは以前のニュースレターでも書いたことがあるのですが、最近とある本を読んだことで、また少し違った視点を得ることができました。今回はその本の内容に触れながら、私なりに考えたことを綴っていきたいと思います。









